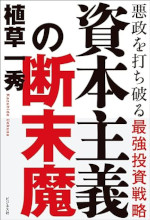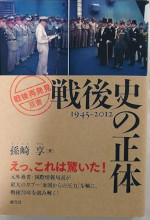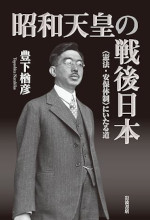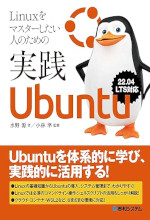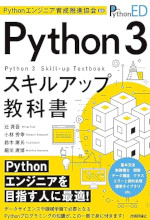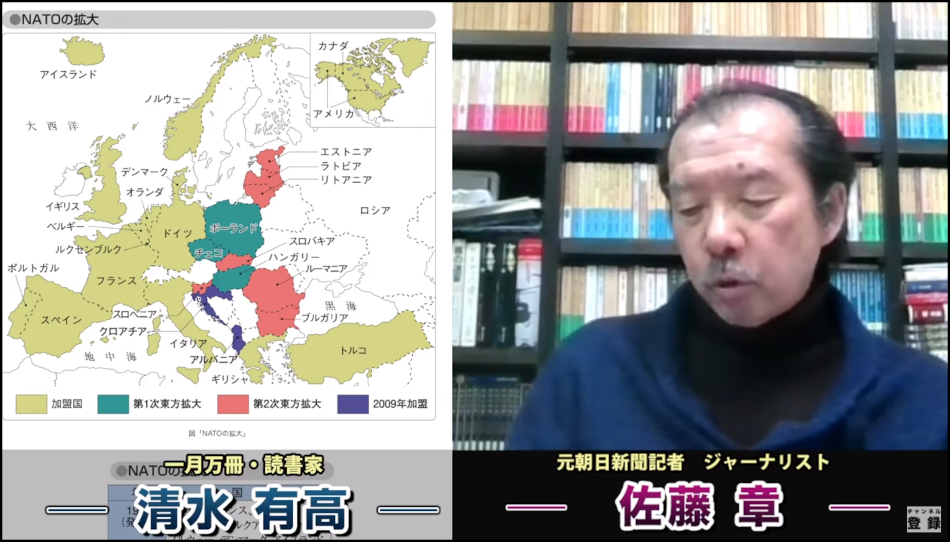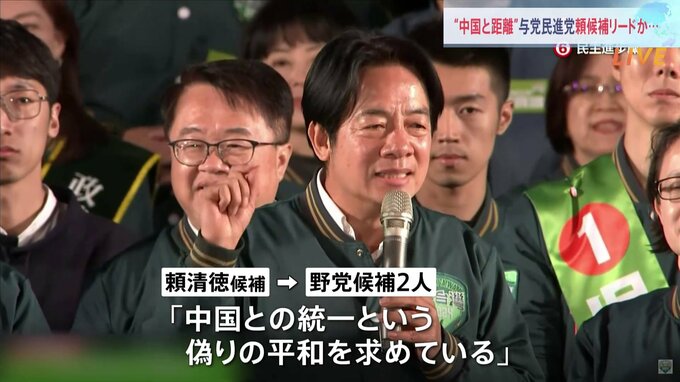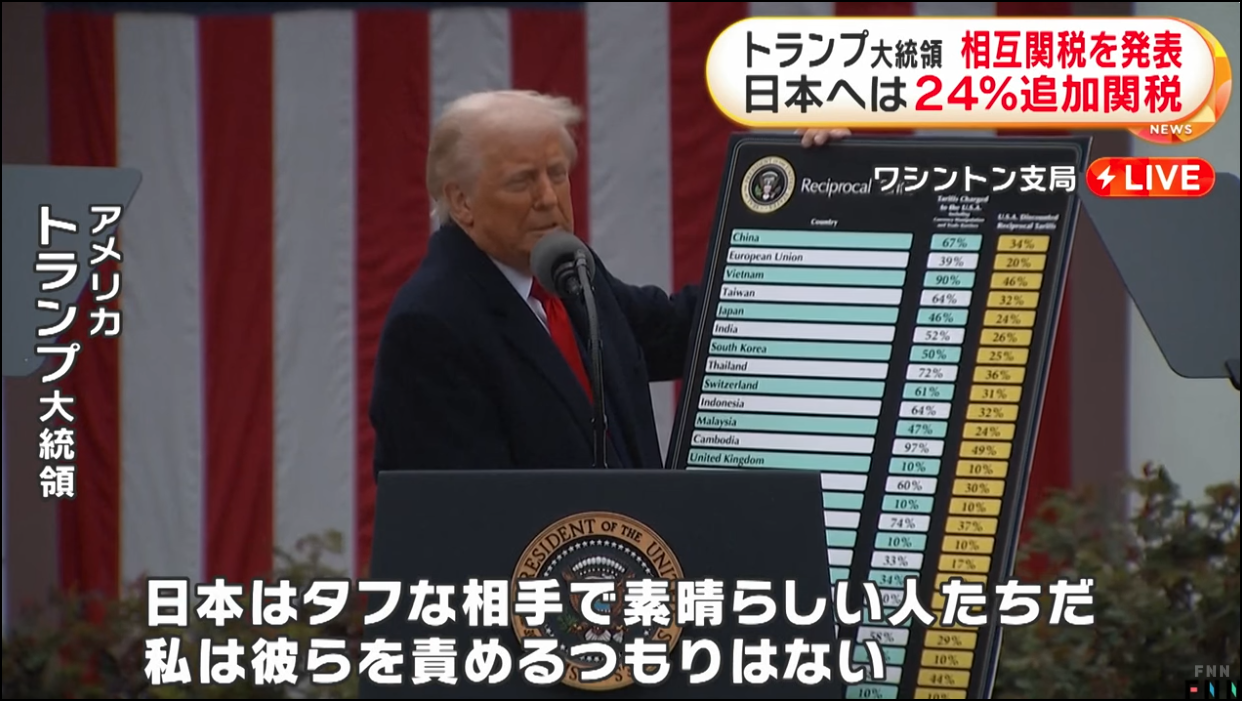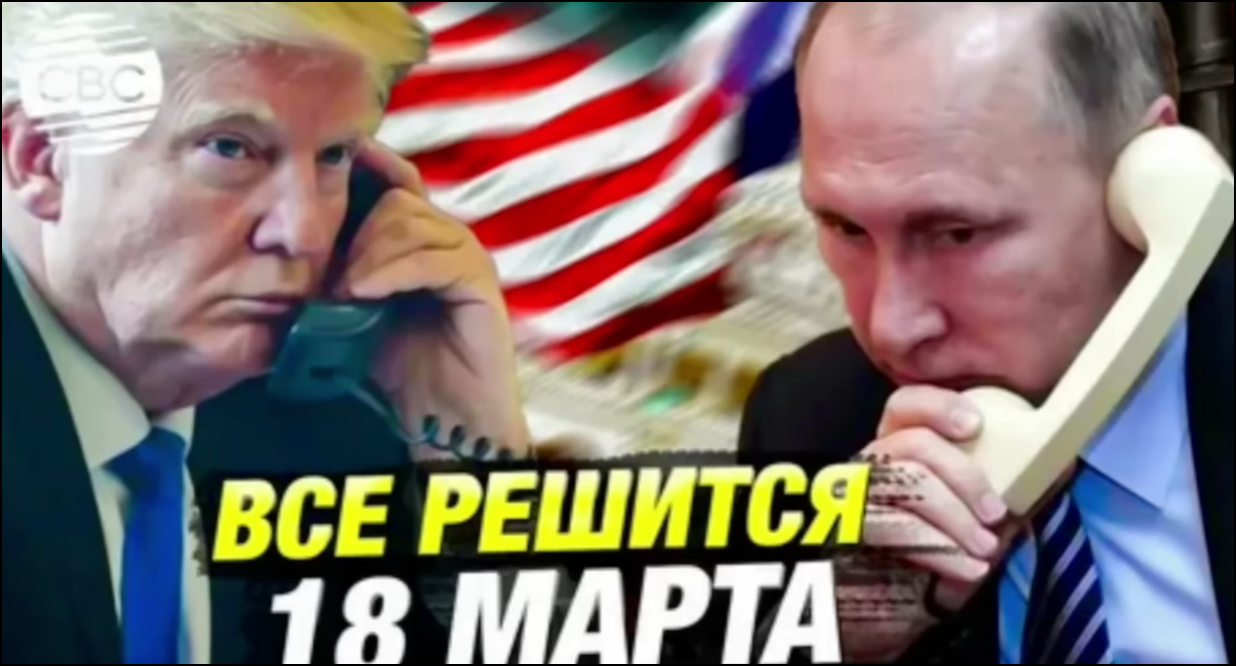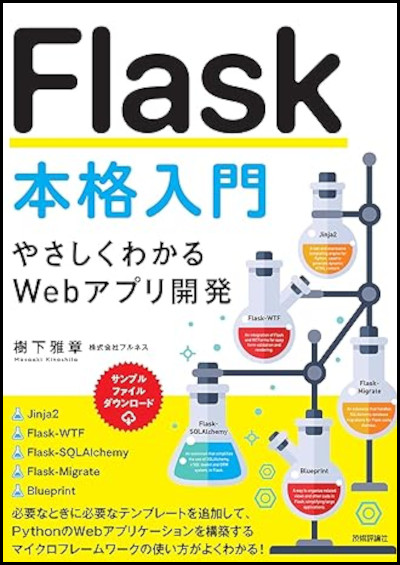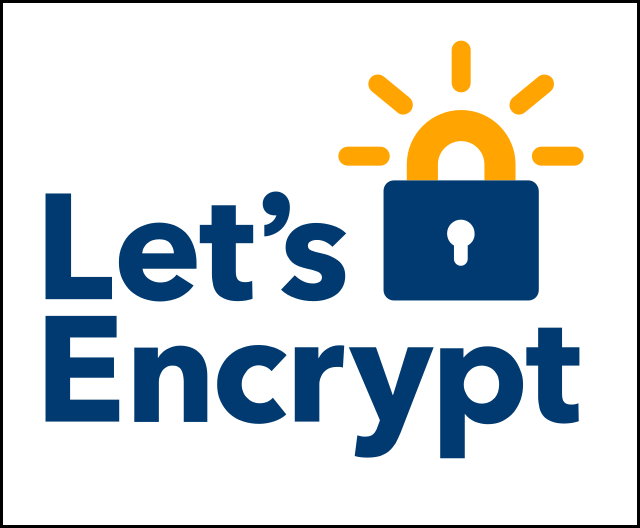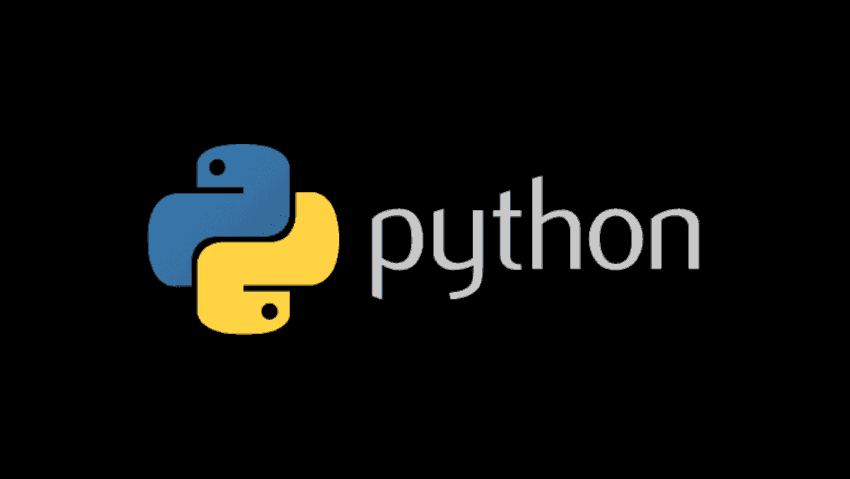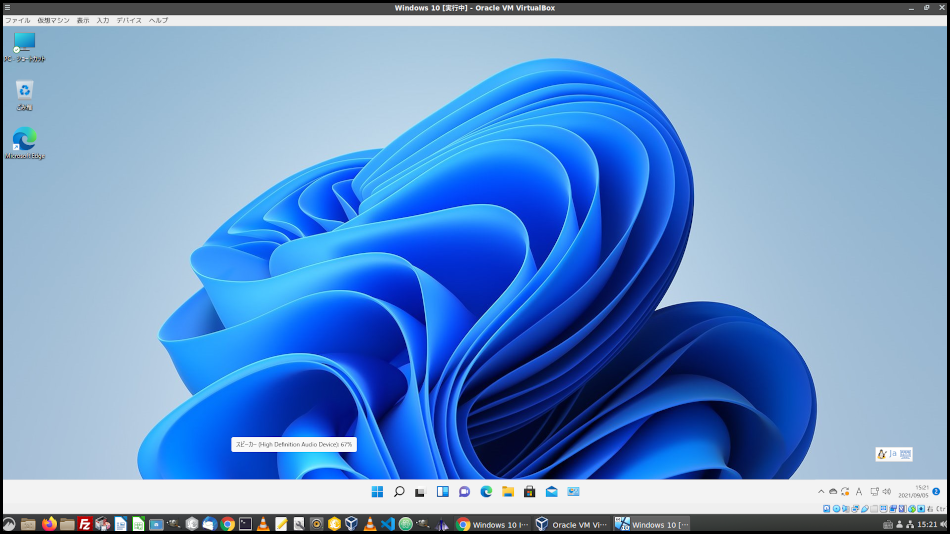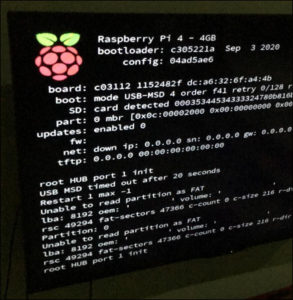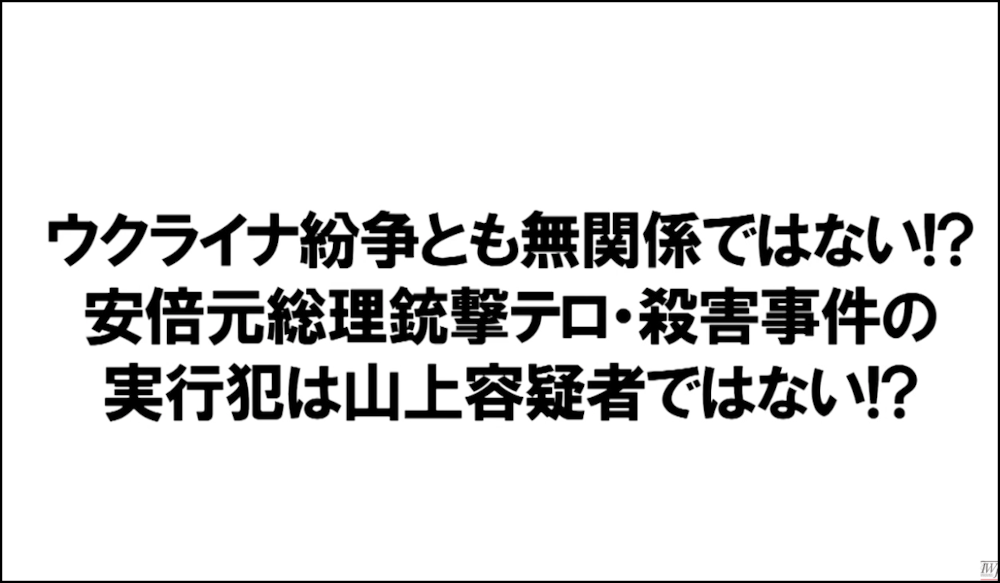さて、統治行為論であるが、これは今回フランスに由来するものとされているが、参考人として呼ばれた慶応大学名誉教授の小林節氏は、「(フランスの学界では)統治行為論は、その反法治主義的な性格のゆえに、むしろ多数の学説により支持されていない」「(フランスの)判例の中には統治行為の概念規定はおろか、その理論的根拠も示されていないうえに、一般に統治行為の根拠条文とされているものが一度も引用されていない」と述べている(「政治問題の法理」日本評論社)。
そして、統治行為論の安易な容認は、「司法における人権保障の可能性を閉ざす障害とも、また行政権力の絶対化を招く要因ともなりかね」ず、「司法審査権の全面否定にもつながりかねない」と警告している。米国では、「政治問題」という概念があるが、これは「絶対的な国益」追求のため、戦争等の事態に対して「大統領に一時的に権力を集中させる」という意味に使われている。日本の「統治行為論」は外国との外国軍についての条約や協定を恒常的に自国の憲法より上位に置くという、立憲民主主義をオブラートに破壊するために使われている。(以上、矢部宏司著「日本はなぜ、『基地』と『原発』を止められないか」集英社インターナショナル社刊行)
日本は敗戦70周年を機会に、日米安全保障条約の「日米友好条約」への改変、国際連合憲章における敵国条項削除の努力を通じての国連中心主義による世界平和への積極的貢献の方向に、外交政策を大転換させるべきである。